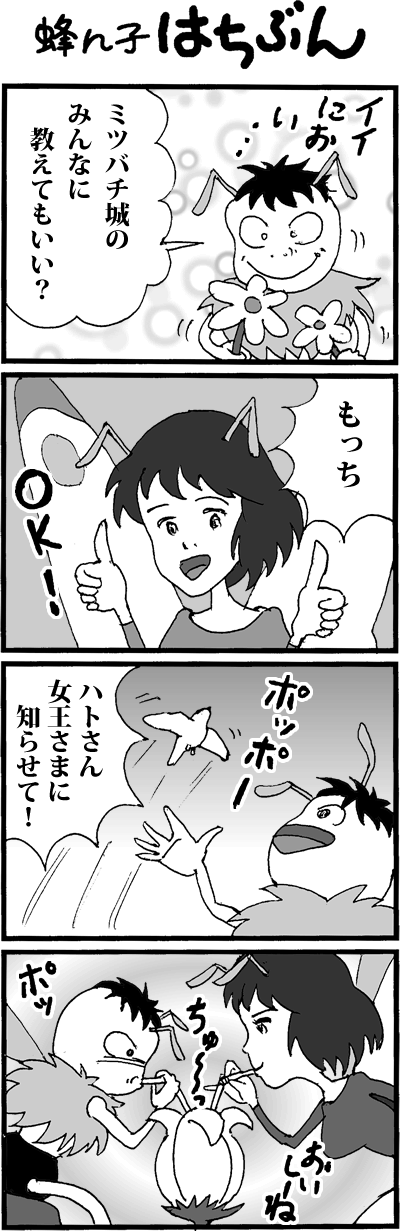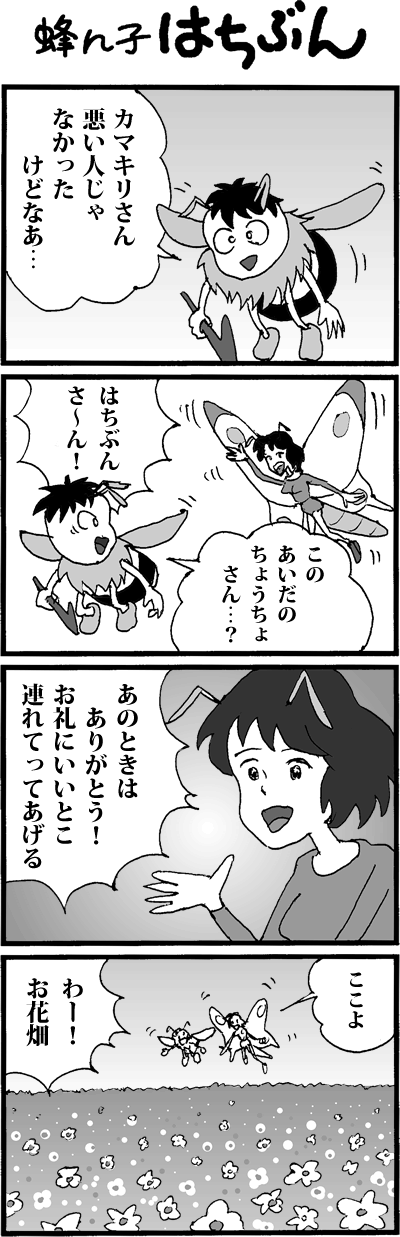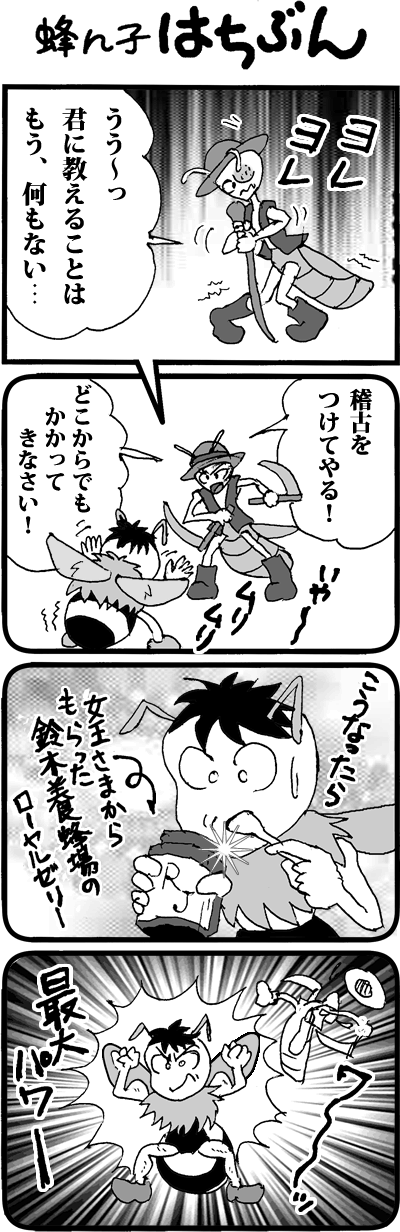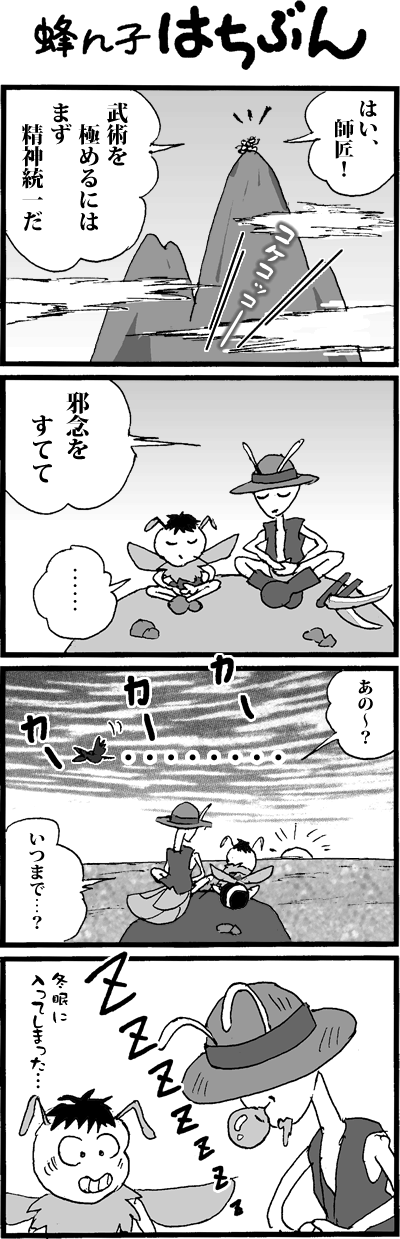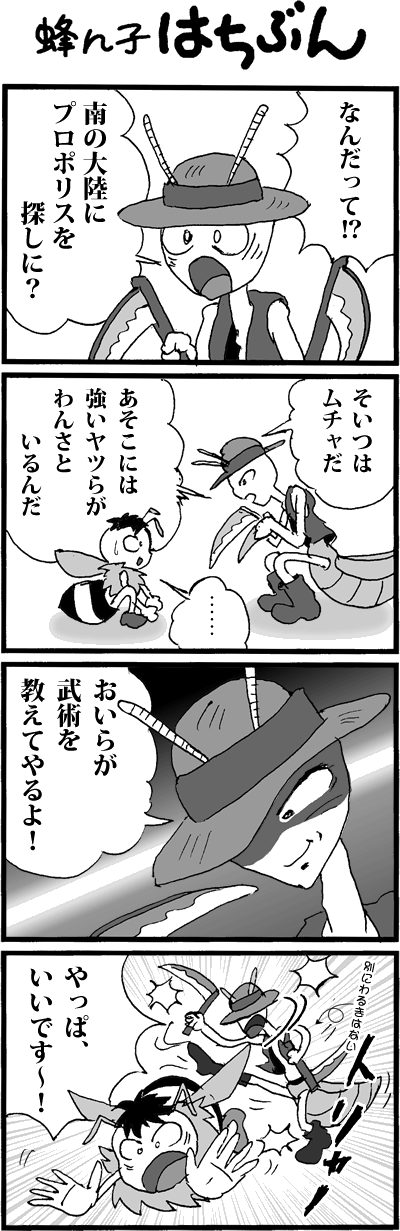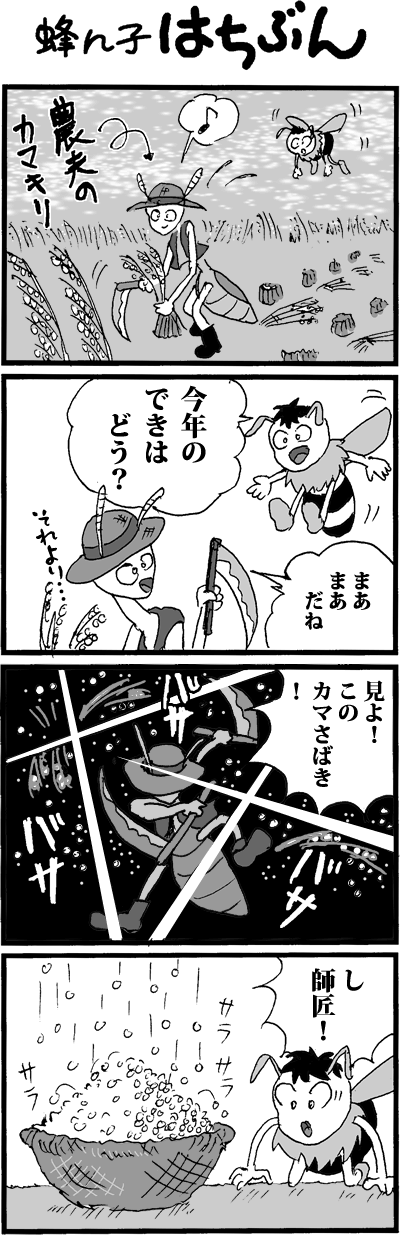鈴木養蜂場はちみつ家の現住所は、
〒382-0082
長野県須坂市大字須坂222-3
当場は長野県の北部、須坂市というところにあります。
人口5万人ほどの市ですが、全国的にはまだまだマイナーな場所かもしれませんネ。(笑)
水利があり桑の栽培適地だったこともあり、明治から昭和初期にかけては全国有数の製糸業の町として栄えましたが、その頃建てられた蔵が今も多く残されており、現在では「蔵の町須坂」という触れ込みで盛んにPRをしていますヨ。
やがて製糸業は廃れていきますが、生産管理技術や工女さんたちの労働力という財産を蓄積した須坂は、第2次大戦になって某大手電機メーカーの工場が疎開する因にもなり、電話機の製造においては全国トップという時代を経、以後、電子機械部品製造の拠点として発展してきました。
ところが長い景気の低迷が続く中で、近年ついにその工場が撤退。それより少し以前から、須坂の商店街は閑古鳥が鳴くような淋しい冬の時代が訪れました。
そんな中、なんとか市を元気にしようと「味噌」を特産品にしようと取り組みはじめましたが、いまひとつ浸透していないような気がします。(笑)
当場の蜂蜜と連携して、須坂特産の蜂蜜味噌ができればいいなあと考える今日この頃です!
今日は当場の所在地についてでした。