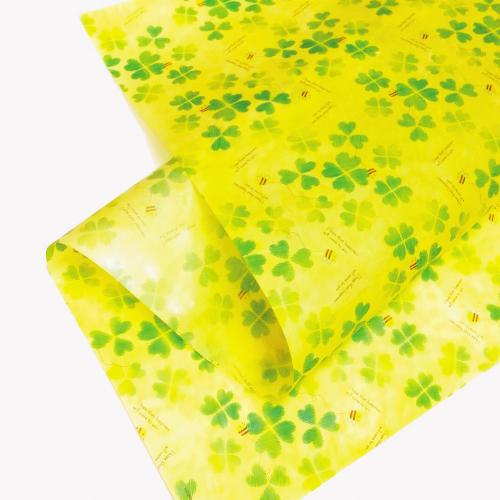はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
プライド
どんぐり子
実家に帰ると、母がパンケーキを焼いてくれた。「たっぷりつけて、元気出しんさい」と、蜂蜜の瓶を置く。落ち込んでいるのをすっかり見透かされている。長年やってきた仕事をAIに奪われそうで、自分の存在が空しく感じられていたのだ。ふと、昔の記憶が蘇った。
母が蜂蜜にはまったのは私が中学生の頃。食卓にパンケーキが登場することが多くなったある日、母は私が食べ終えたお皿を見て、「そんなに残してバチがあたるよ。一匹のミツバチが一生かかって集められる蜜はスプーン一杯程度なんだから」と顔をしかめた。
私は蜂蜜をすくいながらため息が出た。この中に、一匹が採ってきたものはほんの少し。それを見ず知らずの人間が食べているなんて空しすぎる。私がそう話すと母は「蜂蜜はミツバチの唾液と花の蜜が混ざってできる。だから一つとして同じものはないんだよ」と言い、たとえ量は少しであっても自分の蜜が入って唯一の味になるというのはすごく神秘的なことだと目を輝かせた。
「蜂蜜は、ミツバチのプライドよ」
そんな昔の母の言葉を思い出し、ハッとした。世の中に誰がしても同じものなんてないに違いない。そして、それは必ずや何かに影響を与えているはずだと。
ふいに母が蜂蜜の瓶を指さした。
「これ、五年前のものなのよ」
「えっ、大丈夫なの?」
驚くと、蜂蜜は腐ることはなく、年月と共に化学反応が起きて味に深みが増すと話す。
「私の仕事は数年後、どうなっているのやら」
そう苦笑すると、母が言った。
「腐らないのは、本物の蜂蜜だけだからね」
本物の仕事であれば「残る」のだろうか。私でしか生み出せないものが何かしらあるはず……。私に足りないのはプライドなのかもしれない。
パンケーキに輝く蜂蜜が眩しく感じられた。
(完)
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.