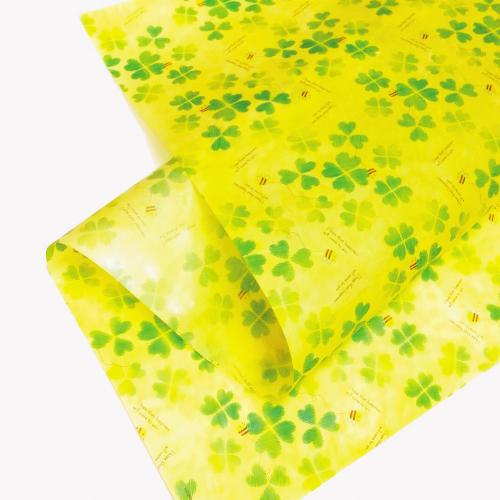はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
あまいあまい蜂蜜
山下 慶将
今となって、僕にとって蜂蜜とは、魔法の液体だ。
世界に存在する蜜の中で、もっとも甘いと言われているらしい。
それもそうだ。あの蜂たちが一生懸命働いて作ったのだから、それは大層、偉大なものであるに違いない。
僕はこれまでの人生の中で、何も意識することなく、その偉大さに気づかず、蜂蜜を食べていた。時に、はちみつレモンジュースという主役級の形で、あるいは、肉料理の引き立て役として、何気なく僕の近くにはいた。しかし、それは他のマヨネーズやケチャップといったような調味料と何も変わらなかった。蜂蜜には、僕の中では、アイデンティティが欠けていた。
ところが、ある出会いが、私の中の蜂蜜という存在を変えた。
それは、ディズニー「くまのプーさん」の本のセリフで、
「友達に会えない日は、はちみつが一滴も残っていない壺のようなものだ。」
である。もちろん、このセリフの意味としては、くまであるプーさんが、友達に会えない日があると、彼がこよなく愛している蜂蜜がまるで空っぽのような喪失感になってしまうということである。しかし、私が注目したのは、なんでこの作品には、このような素晴らしいものとしての蜂蜜が描写されているのだろうという点である。くまが蜂蜜を好むことは言うまでもないが、蜂蜜には他には変えられない魅力がある。それはやはり、甘さだろう。
蜂蜜に代わるものを考えた人がどのくらいいるだろう。いや、それは不可能なことなのだろうか。僕が思いつく限りでも、あんみつレモンジュース。さすがに無理がある。考えてみると蜂蜜に匹敵するものなんてない。
僕はどうして、蜂蜜の良さに、魅力に気づかなかったのだろう。今は、無知だった自分への罪悪感がありつつも、いつも食卓にいる身近な存在だ。
いつもありがとう。
君に代わる存在はいないよ。
僕はそう思いながら、今日も蜂蜜を味わうだろう。

(完)
ツイート
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.