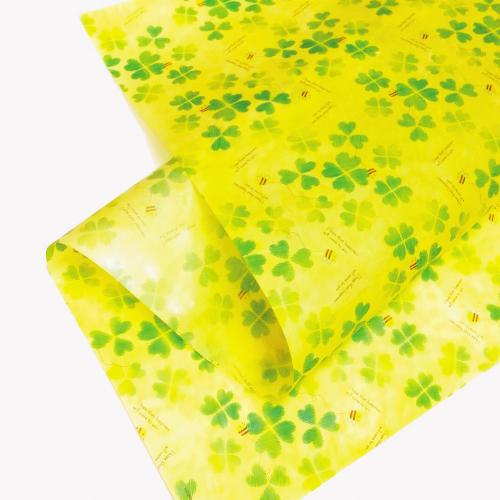はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
一さじの琥珀に宿る、命の記憶
華盛頓
朝、起き抜けの白湯を飲み干した後、私は決まって木製のスプーンで蜂蜜をひとすくい口に含む。とろりとした黄金色の雫が舌の上で広がり、花の香りが鼻腔をくすぐる瞬間、身体の奥底から静かな力が湧いてくるのを感じる。それは単なる糖分の摂取ではない。何千、何万というミツバチたちが、広大な空を飛び回り、無数の花々と対話して集めた「時間の結晶」をいただいているという感覚に近い。
ミツバチという生き物は、不思議なほどに献身的だ。一匹の働き蜂が生涯をかけて集められる蜂蜜の量は、ティースプーン一杯にも満たないと言われている。つまり、私が毎朝何気なく口にしているあの一口は、数匹の蜂がその命を燃やし尽くして成し遂げた、生涯の労働の集大成なのだ。そう思うと、その甘さは急に重みを増し、畏敬の念すら抱かせる。
蜂がもたらす恵みは、甘美な蜂蜜だけにとどまらない。彼らの巣箱は、生命を守り抜くための驚くべき知恵に満ちている。例えば「プロポリス」。蜂が樹木から集めた樹脂と自らの分泌物を合わせて作るこの物質は、巣を無菌状態に保つための天然の防御壁だ。外敵やウイルスから群れを守るその強固な守りは、現代を生きる私たちの身体にとっても、頼もしい盾となる。特有のピリッとした刺激を感じるたび、厳しい自然界を生き抜く彼らの「拒絶と守護」の意志に触れたような気がするのだ。また、ニュージーランドに咲く花から採れる「マヌカハニー」もそうだ。荒野に自生するマヌカの木から運ばれたその蜂蜜は、薬のような独特の風味と共に、傷ついたものを癒やす力強い野性を秘めている。
そして、巣の奥深くには、生命の神秘そのものが横たわっている。女王蜂だけが食すことを許された「ローヤルゼリー」。同じ遺伝子を持って生まれた幼虫が、この乳白色のクリームを与えられるか否かだけで、働き蜂になるか、あるいは群れを統べる女王になるかの運命が分かれるという。それはまさに、可能性の扉を開く魔法の鍵だ。さらに言えば、古来より人々が貴重なタンパク源として、あるいは滋養強壮のために食してきた「蜂の子」もまた、凝縮された生命のエネルギーそのものである。見た目に尻込みする人もいるかもしれないが、その小さな身体には、これから羽ばたこうとする未来への爆発的な力が詰まっている。それをいただくことは、彼らの時間を自らの命に継承する儀式のようなものかもしれない。
人間は太古の昔から、この小さな隣人たちが作り出す恵みに頼り、癒やされてきた。甘美な蜂蜜、守りのプロポリス、癒やしのマヌカ、生命の源泉たるローヤルゼリーや蜂の子。これら蜂産品の一つひとつには、自然界の循環と、小さな身体で懸命に生きた彼らの記憶が刻み込まれている。
スプーン一杯の琥珀色を見つめ直す。そこには、太陽の光、咲き誇る花々、風の音、そして無数の羽音が溶け合っている。「いただきます」私は今日も、その小さなスプーンに深い感謝を込め、彼らの命のかけらを私の命へと結ぶ。甘く、力強い自然の祈りが、身体の隅々まで染み渡っていくのを感じながら。
(完)
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.