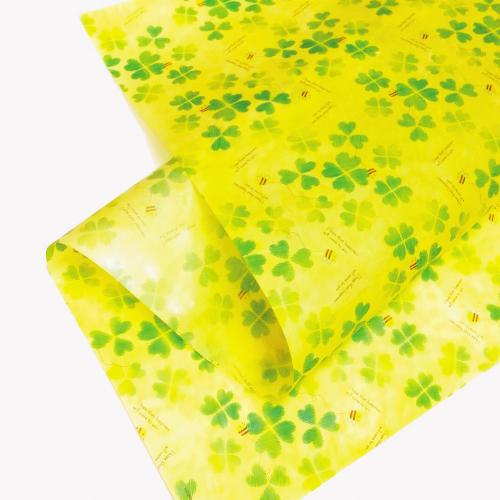はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
魔女のおくすり
七尾 百合子
「お母さん、これなあに?」
食器棚のすみに、見慣れない白い箱がある。開けてみると、一錠一錠こわけにパッケージされているそれは、お菓子ではないようだ。
「ああ、大人用のお薬よ。魔法のお薬。飲んじゃだめよ」
母は慌てて私の手から取り上げる。
食いしん坊の私は、なんでも食べるから、警戒しているみたい。
言われなくても、乳白色のカプセルは、あまり美味しそうではない。肝油が大好きな私は、「そんな言い方しなくてもいいのに」と、唇をつきだす。
小学校2、3年生の頃だったと思う。
毎朝、母は「今日は晴れそうよ」とか「雨が降りそうだから、折りたたみ傘を持っていきなさい」と、予言する。それがいつもピタリと当たる。私にとって母は、魔法使いや魔女みたいな、すごい力を持つ人だった。
「あのお薬は、お母さんに魔力を与える薬に違いない」
なんとなく、そう思わずにはいられないような、高そうな包装だ。私は母が魔法の薬を飲むたび、じいっと見た。けれど、自分はこっそり飲もうとは思わない。
(子供の私が飲むと、きっと魔力が多すぎて、死んじゃうんだ)
ところがある日、母が予言していなかった夕立が降り、私は駆け足で帰る。びしょぬれになってしまった。
「魔女の予言がはずれた……」
ショックを受け、立ちすくむ。母は(天気予報を見ていたのだろうけれど)とうとう、予言をはずしたのだ。
それ以来、母がローヤルゼリーを飲んでも、気にならなくなった。母にとっては美肌や、冷え性の効果を狙っていたかも知れないから、魔法のお薬だったのだろう。
いま、自分もローヤルゼリーを必要とする年代になった。
そんなときは、魔女の娘の私にも効きますように、と飲む前に願う。
その薬は、自分の幼さと、慌てて取り上げた母のことを、顔をほころばせて思い出させてくれるものなのだ。
(完)
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.