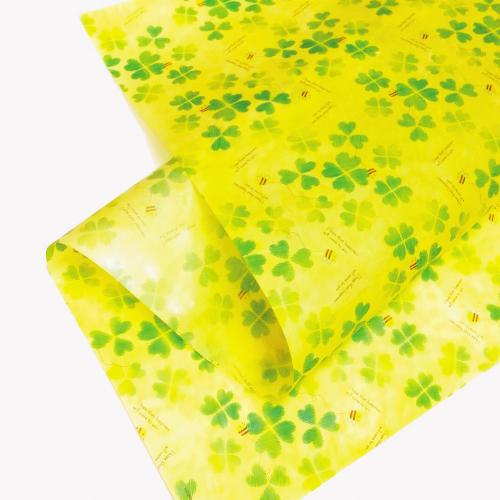はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
無題
θ
朝。ほんのり狐色に焦げたパンに、バターがじゅわぁと滲みる音がする。祖父がスプーンいっぱいに乗せたアカシアの淡い黄色が、とろとろと螺旋を描いてパンに溶ける。大きな一口で頬張ると、甘い甘いハチミツが上品に舌を解いていくのだ。どこかで聞いたフランスの貴族になったみたいで、この瞬間が一番好きだった。「りすみたいだなあ。」と祖父の冗談が聞こえる。家族の笑い声が、顔を照らす暖かな朝日が、そんな幸せな毎日が。大好きだった。
「ねえ、おじいちゃん。もう起きてもいいんだよ。」あの日と同じ暖かな小春日和の中で、祖父だけがまだ目を覚まさない。沢山のチューブと大きな酸素マスクに囲まれた祖父は、一回り小さくなった気がする。祖父が突然倒れたのは、いつも通りの夕方だった。笑顔で電話を取ったはずの母が、さっと顔色を変え泣き出す。初めて聞く祖母の取り乱した声。「心肺停止」という単語がすっと心を冷やした。慌ただしく実家に帰った母を見送り、私はしばらく何も考えられなかった。嘘だ。嘘に決まっている。今日の朝電話をして、元気な声を聞いたのだから。
三日たっても祖父は目を覚まさなかった。倒れた原因はもう分からない。こんなご時世なので、タブレット端末での面会しかできないが、祖父はただ眠っているように見える。朝食のパンに、ふと蜂蜜をかけようと思ったのは、蜂蜜が大好きな祖父の笑顔が、思い出されたからかもしれない。昔と変わらず優しい黄色で溶ける糖蜜を見て、昔祖父が教えてくれた話を思い出した。
「知ってるか?蜂が一生のうちに集められるハチミツはティースプーン一杯くらいなんだ。だからこの小さな瓶でも沢山の命が込められてる。」そう言って笑顔で続ける。「それをあたりまえみたいに食べてる事は、奇跡なんだよ」
あたりまえは奇跡。ただ見えていないだけで、本当は「あたりまえ」なんて無いのかもしれない。コロナが猛威を振るうこの二年間、ニュースでは「日常が崩された」「あたりまえの毎日を取り戻すために」と言っている。でも。今大切な人たちと笑い合って、遊んで、健康でいる毎日は、小さな奇跡の詰め合わせだ。私たちはつい忘れてしまう。蜂蜜に込められた沢山の奇跡の様に。
じゅわぁ。口に広がる優しい甘さに、ただ涙が止まらなかった。
(完)
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.