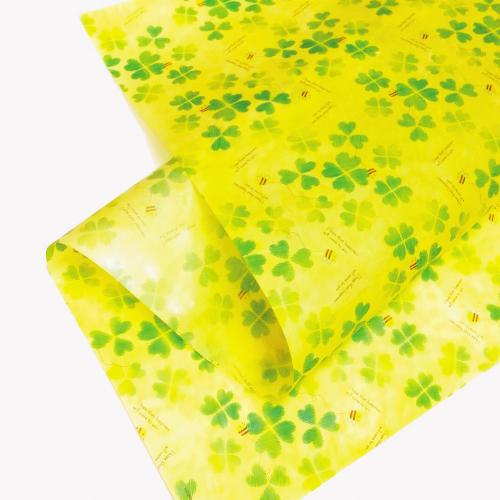はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
蜂蜜が棚に置かれた日
吾妻 ひろみ
朝が苦手だった。四苦八苦したけれど、心や環境や年齢が変わったから今はわりあい起きられる。ただ四苦八苦したうちの一つ、朝一杯のコーヒーを飲むことは、習慣として定着した。
たいていはインスタントになる。プリンにしっぽをつけたような形の洒落たやかんで湯を沸かして、インスタントコーヒーをコップ半分まで溶かし、残りを牛乳で充たして飲んだ。ほぼ毎日それを飲んでいた。
すると兄に伝播した。
「わけて」
「ん」
次第に言葉なしにインスタントコーヒーを兄が使うようになり、ついには使い切り、と思えば新しいコーヒーの瓶を買ってきた。こちらも買ったらふたつになった。
ある朝の台所、兄の懐に、何やら見知らないチューブが置かれていた。
「なんそれ」
「はちみつ」
「いれるん?」
「る」
「へぇ」
ちょうど湯が沸き、兄は、こちらの感覚としては多めのインスタントコーヒーをマグカップに放る。湯を注ぎ牛乳で充たす。
蜂蜜の包装ビニールを剥ぎ、蓋を開ける。習慣に変化がもたらされるにしてはあまりに呆気なく、蜂蜜を垂らし入れた。
「多くね」
「こんなもんしょ」
兄は金属製のスプーンを取り出してかき混ぜる。蜂蜜を棚に仕舞おうとする。
「あ待って、つかうわ」
「つかえ」
同様にしてコーヒーを淹れ、やはり呆気なくはちみつを垂らす。普段はかき混ぜたりしないものだから、スプーンがよそよそしく見える。
兄は飲み終わって、隣のシンクにマグカップを置いた。
「どう」
「ヤサシーあじ」
「多すぎじゃね」
「や、ちょうど」
疑って、自分の感覚に即した量のはちみつを入れた。スプーンを引き上げると、うっすらと飴色の膜が張っていた。舐めると優しい味がした。
インスタントだから深くまで味わおうとすると損をする。ぐいぐいぐいと三口で飲み干した。心持ち、味が丸くなった。もう少し入れれば良かったと、コーヒーで暖まった息を吐きながら思った。
コップの底を這う飲み残しが普段よりはほんの少し粘り気を持って艶を増していた。
「すくなかったでしょ」
「すくなかった」
次の日、わけて、と言って蜂蜜を分けてもらった。
(完)
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.