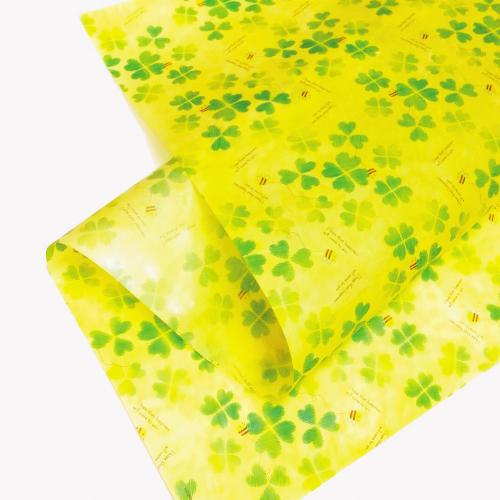はちみつ家 > 蜂蜜エッセイ


蜂蜜エッセイ応募作品
「盗蜜」といわれる蜂の行動
渡辺 碧水
北海道新聞の二〇二〇年十月二十七日夕刊のコラム「まど」欄に「ハチの盗蜜」の話題が載った。
九月初旬、北海道別海町野付半島の浜辺で、希少在来種のノサップマルハナバチが受粉をしないで「盗蜜」を行う瞬間を、地元中標津町の写真家 ・前沢卓さんが初めてカメラに収めたという。
その日、小さなラッパ形の黄色の花を持つウンランに、蜂(ノサップと外来種のセイヨウオオマルハナバチ)が群れていた。
両種とも、花の下の細い管状部に口吻で穴を開けて蜜を吸う「盗蜜」をしていた。ノサップは普通に花の上から蜜を吸うと聞いていたから、前沢さんは驚いたそうだ。
両種とも口吻が短い。ノサップがセイヨウを真似たのかどうかは不明だが、この時期に唯一開花するウンランの蜜を吸う工夫だったのかもしれないと推察し、秋の浜辺で生き残りを競う両種の様子を語っている。
この記事を読みながら、浅識の私は、こうした蜂の行動を「盗蜜」というのだろうか、「吸蜜」とみなしてはならないのだろうかと、ふと疑問を感じた。
そして、「盗蜜」とは、他の蜂の巣の蜜を盗み取ることではなかったか、とも。
調べてみると、新聞記事の表現のほうが当を得ていた。動物行動学では「昆虫や鳥などの動物が受粉を行わず花蜜だけを奪うこと」の意味で使う用語だそうだ。
花で蜜を分泌する被子植物は、その蜜で動物を誘い(蜜を動物に提供し)、動物に花粉の転送を行わせる(手伝ってもらう)ことで共に進化してきた、との理解に立つ。
植物と動物の共存共栄関係からは、蜜だけを奪って受粉に関与しないのは不適切行為(盗蜜)とみなすわけである。
そこには、自然な生存の採餌行動とは寛容にみなさない厳格な目が光っていた。
一方、養蜂業界語では、蜜蜂が他の個体や巣箱から蜜を奪うこと(他群の貯蜜や給餌した砂糖水を盗む行為)を「盗蜜」という慣例もあるようで、全くの誤解ではなかった。
だが、蜜蜂同士の争いは、同じ巣の中ではなく「巣対巣」の蜂群間で起こる餌の略奪。このことから、養蜂用語では「盗蜂」というのだそうだ。
(完)
蜂蜜エッセイ一覧 =>
蜂蜜エッセイ
応募要項 =>
Copyright (C) 2011-2026 Suzuki Bee Keeping All Rights Reserved.